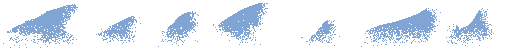日本勤労者山岳連盟創設者・伊藤正一は1946年以降、三俣山荘、湯俣山荘、雲の平山荘を整備、建設。日本の大衆登山の発展に尽力した。その不思議な体験を二話。
『黒部の山賊』(伊藤正一、山と渓谷社)
遭難者のお礼参り ―いちばん不思議だった話―
.....
話は昭和三十九(一九六四)年九月二十四日、三俣山荘でのことである。昨夜からの宿泊客はなく、鬼窪、小林ら五人が小屋番をしていた。前日から寒風が吹きすさび、雪がはげしく舞っていた。そんな早朝に三人組の女性が助けを求めてきた。
彼女らは看護婦のパーティで、前日の二十三日に太郎平を出発し、黒部五郎小屋を過ぎて三俣山荘に向かう巻き道にはいり、尾根から一段下った所まで来たが雪のため視界がきかず、幕営したという(そこは晴天ならば眼下に三俣山荘が見えて、山荘までは約一五分で下れる所である)。すると彼女らのテントヘ疲れきった一人の若い男性(S君としておこう)がころがりこんできた。話によると、S君は太郎平からそこまで三日もかかって来たらしい。
「とにかく彼は衰弱しきっているから、すぐに助けに来てほしい」と彼女らの話だった。
山荘からすぐに二人が救援に行って、S君をつれてきた。二階に寝かせて介抱したが、衰弱していて固形物は食べられないので、主としてグラタンなどを食べさせていた。介抱のかいあって、S君はしだいに体力を回復し、二十七日ごろからは自分で歩いてトイレにも行かれるようになった。
〃この分なら、まもなく自力で下山できるようになるだろう″と一同は安堵の色を見せていた。
二十九日の朝になってS君は、いたって元気そうに「おかゆを食べたい」と言ったので、小林が厨房へおかゆを作りに行き、その間鬼窪が付きそっていた。すると突然、S君の息づかいが荒くなってきた、と見るまに、たちまち彼の呼吸は停止してしまった。ほんとうにあっと言う間の出来事だった。
.....
一年が過ぎ、黒部源流にはまた紅葉の季節がおとずれた。この辺の紅葉は、いつ見ても美しい。常緑のハイマツにダケカンバや草の葉の黄色。それにナナカマドが真紅の色を添える。そしてその年もまた前年とまったく同じように、紅葉の上に新雪が積もった。
三俣山荘には鬼窪と小林だけがいた。彼らは前年の出来事などまったく忘れて、三階に寝ていた。つまりS君が寝ていた付近である。
二人が眠りにつこうとしていたころ、外でガヤガヤという人の話声とともに、足音が近づいて来た。
「おい、だれか来たようだぞ」
「今ごろキャンプの連中だろうか」
と話し合っていると、足音は玄関の所まで来た。ガラリ、と戸を開ける音がして、
「こんばんは、こんばんは」と大きな声がする。
鬼窪が下りて行って見たがだれもいない。不思議に思って、玄関の戸を開けて外を見た。やはりだれもいない。玄関の周囲の処女雪の上をよく見たが、どこにも足跡はない。
「おい、そういえば去年、 一人死んだじやねえか」と鬼窪。
「そうだ、今日は九月二十三日だ」と小林。
二人はそこそこに布団をかぶつて寝てしまった。ところが翌朝である。
「ありがとうございました」と玄関で大声がして、ガラリと戸が開き、だれかが出て行った音がする。
今度は小林が下りて行って見たが、だれもいない。外を見たが雪の上に足跡はなく、やはりだれもいなかった。
これは実に不思議な出来事だったが、その時点でわれわれはただ一度だけのことだと思っていた。ところが翌昭和四十一年九月二十三日にも「こんばんは」の声はやってきたのである。これは実におどろきだった。そして次の年からは、われわれのほうからその声の来訪を期待するようになった。
毎年九月二十三日になると、その声は期待どおりにやってきた。そして最後に来たのは昭和四十四年だつた。そのときは、ひときわ明瞭に「ありがとうどざいました」と何回もくり返して去って行った。気のせいか、そのときの語調は満足気であり、″これで気がすんだ〃と言いた気だったように思えた。そして次の年からは、九月二十三日になっても、三俣山荘でそれらしい物音は聞かれなくなった。
ところがこの話はさらに後まで続くのである。昭和五十二年だったと思う。八月上旬の忙しいときだった。私が三俣山荘の受付にいると、 一人の登山者が話しかけてきた。
「こういうことおぼえておられますか。十何年か前のことですが、雪の降るなかを黒部五郎の方から来た一人の登山者が、この小屋で亡くなったことを……」
彼はS君の友人だという。
「ええ、ええ、おぼえているどころか、実は……」と私はその後の出来事を話し、特に最後には、ありがとうございました」と明瞭な声で言って去って行ったことを彼に告げた。実はそのとき、私は彼がさぞ驚くであろうことを内心期待していたのである。
ところがその友人は平然とした表情で、
「ええ、そうでしよう。あいつはそういう義理堅いやつなんですよ」
と言った。
これには私のほうが驚いてしまった。そして彼からもっとくわしく話を聞きたいと思ったが、あいにく受付のラッシュどきだったので、″あとで″と思い、彼の宿泊カードにチェックを入れておいた。しかしその日は話し合う機会がなく、彼は翌朝早くに出発してしまった。さらに残念なことに、私は後にその日の宿泊カードを調べたが、どうしたわけか、チェックしておいたものが見つからなかったのである。
(初:『山と渓谷』昭和六十年五月号 通巻五八八号) 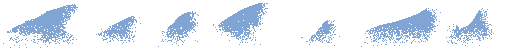
神かくし?−−昭和38年夏、富山県警から三俣山荘へ雲の平で白骨が発見されたので処置するよう電話が入った、その矢先・・・−−
カベッケが原でキヤンプをした金沢大学医学部の学生I君、S君、B君の三名は、夕方雲ノ平山荘に着いた。彼らは疲れていたので、小屋へ着く手前、約十分のところにリュックを一つ置いてきた。そこでいちばん元気のよかつたI君が一人でそれをとりに行った。それっきりいなくなってしまったのである。天気はよかったし、暮れるにはまだ充分に時間があった。小屋から十分といえば、万一のときでも呼べば充分に聞こえるところである。ほかにも登山者は大勢いた。
I君がいなくなったといってさわぎだしたのは暗くなってからだった。小屋の者がライトを持って行ってみると、リュックはそのままのところに置いてあった。そしてそこはまさに白骨(富山県警から処理依頼があった)のある藪の入口だったのである。
ただちに捜索が開始された。そのとき小屋にいた登山者の中から十数名の協力を得て、営林署四名、小屋の者十名、それにS君、B君、その他合わせて四十名以上の人数が動員された。
まだ遠くへは行くまいというので手分けをして、大声で叫びつつ、その夜のうちに雲ノ平のほとんど全域を歩きつくしたが、なんの手がかりも得られなかった。
翌日も未明から捜索はつづけられた。藪の中もくまなく探し、周囲のすべての小屋へは伝令がとんだが、やはりわからなかった。
三俣からの電話連絡で急を知った下界では、ただちにラジオでそのことが報道され、金大医学部の救援隊十名が出発し、飛行機が一台飛んできて、黒部源流一帯に、I君あてのビラをまいた。しかしその日もまた徒労に終わつた。
・・・・・
その翌日も同様だった。もうわれわれは考えようもなくなっていた。忍術使いのように消えてなくなったとしか思いようがなかった。
四日目の朝。今日も捜索隊が出発しようとしている小屋の玄関へ、当のI君が、ふらっと帰ってきた。
・・・・・
そして彼の話はこうだった。
小屋から出て、リュックを置いたところの近くまで行くと、霧がかかってきて方角がわからなくなってしまった。それからあとは、ただ小屋へ帰ろうと思って藪の中を歩きつづけたことだけしか記憶にないという。
さらに彼のことばをよく聞いて判断すると、霧は白骨のほうからかかってきたらしい。しかし不思議なことに、そのころ雲ノ平で霧を見た者は一人もいないのである。そして藪の中を歩いて最後に出たのは、カベッケが原だった。そこでキャンプをしていた人たちの中へ入れてもらって最後の夜は過ごし、早朝雲ノ平へ登ってきたのである。そして彼は、
「いまになって考えてみると不思議です。昼も夜も、いつも四人で、話し合ったり僕の持っていたカンパンを食べたりしながら歩いていたので、少しも寂しくありませんでした」と言う。
.....
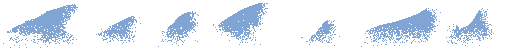
|